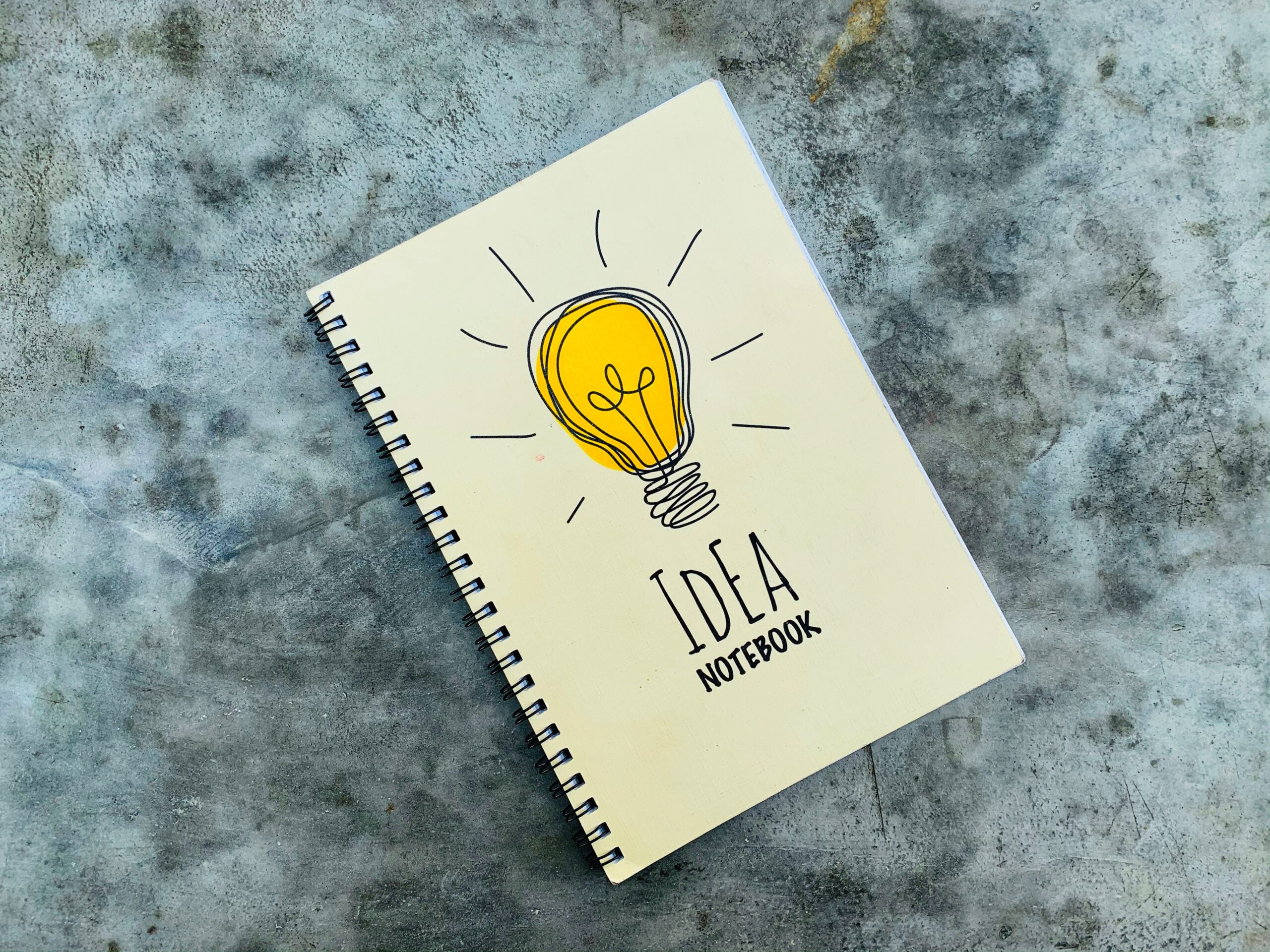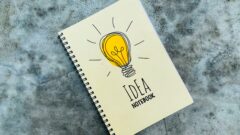ビタミンとスキンケアの深い関係
貴方は「ビタミン」と聞いてどんなものを思い浮かべますか。おそらく、多くの方がドラッグストアで売っているサプリメントを想像するのではないでしょうか。忙しかったり1人暮らしだったりするとつい不規則になりがちな食事を補うために、「マルチビタミン」「ビタミンC」「ビタミンB」など様々なビタミンのサプリメントが販売されており、多くの方に愛用されています。
そんな「ビタミン」ですが、化粧品成分としてもお馴染みの存在です。化粧品に馴染みのない男性の方でも、化粧水などに含まれている「ビタミンC誘導体」の名称は聞いたことがあるのではないでしょうか。また、少し化粧品に詳しい方であれば、オイルやクリームなどに含まれている「ビタミンE」(トコフェロール)、一部のスキンケア製品に利用されている「ビタミンA」(レチノール)のこともご存知かもしれません。一体、化粧品に利用されているビタミンはどんな種類があり、どんな目的で利用されているのでしょうか。
ビタミンの配合目的①酸化を防ぐ「ビタミンC」「ビタミンE」
ビタミンを化粧品に配合する目的の1つは「酸化を防ぐ」ことです。化粧品を使い切らずに放置してしまい、久しぶりに使おうとしたら匂いや見た目が変わっていた、あるいは肌につけたら刺激を感じた、といった経験をした方もいらっしゃることでしょう。この好ましくない変化は主に空気中の酸素と化粧品の成分が反応する、いわゆる「酸化」と呼ばれる現象によって引き起こされます。また、空気中の酸素は紫外線などによってより反応性の高い「活性酸素」と呼ばれる状態へと変化し、皮膚細胞を酸化することによって肌のシワやシミ、くすみなどを引き起こしてしまいます。
化粧品のビタミンC、ビタミンEは「酸化を防ぐ」上で大変重要な役割を果たします。これらの成分は前者が水に溶けやすく、後者が油に溶けやすい点で異なっていますが、いずれも「酸化されやすく」「酸化の連鎖反応を引き起こさない」性質を持っているため、配合することによって優先的に酸化され、化粧品自体の酸化による品質劣化を防ぎます。また、肌につけると活性酸素による皮膚細胞の酸化も防ぐ作用もあるため、肌のシミやくすみを予防する「美白」やシワやたるみを予防する「抗老化」の効果があると言われています。ビタミンC、ビタミンE以外では、ビタミンB群に分類されるナイアシンアミドや葉酸にも同様の効果が期待できます。
肌の再生を促す「ビタミンA」「ビタミンB」
多くのスキンケア製品に含まれている成分と同様に、化粧品におけるビタミンの役割は肌のトラブルを「防ぐ」ことが中心です。しかし、一部のビタミンは皮膚の細胞に直接作用することによってターンオーバーを活性化し、「肌の再生を促す」効果があることが知られています。
代表的な成分としては「ビタミンA誘導体」もしくは「レチノイド」として知られるレチノールやパルミチン酸レチノール、酢酸レチノール等が挙げられます。これらは肌表面で酸化され、皮膚のレチノイン酸受容体と呼ばれる部分に働きかけることによってターンオーバーを促進し、古い角質を剥がしたり、肌内部でのヒアルロン酸やコラーゲンの産生を促進したりする作用があることが知られています。ビタミンA誘導体の中でもレチノールは医薬品にも利用されている成分で、シミやシワなど様々な肌の悩みに効果を発揮しますが、その作用がレチノイド反応(肌の皮むけや赤み)を引き起こすこともあるため、使用にはやや注意が必要な成分です。
また、ビタミンB群にも肌のターンオーバーを促進する作用があることが判っています。代表的な成分としてはナイアシンアミド(ビタミンB3)やパンテノール(プロビタミンB5)が挙げられます。ナイアシンアミドは皮膚のみずみずしさやハリを担っているコラーゲンやセラミドの生成を助ける作用があることが判っており、先述した抗酸化作用と合わせて肌の状態を改善する効果が期待できます。また、パンテノールは肌や髪に浸透し、高い保湿作用を示すだけでなく、身体がエネルギーを産み出す仕組みの1つである「クエン酸回路」を助け、新陳代謝を促進する効果があることも知られています。これらの効果はビタミンA誘導体と比較すると穏やかですが、その分安全に使うことができる成分として利用されています。
肌に良いビタミンは他にもあるの?今後の可能性は?
一般的に化粧品成分として利用されているビタミンは先に挙げた4種類ですが、もう2種類のビタミンである「ビタミンD」「ビタミンK」も肌にとって嬉しい効果を持ち合わせています。
ビタミンDは体内に取り込むことで抗酸化作用、抗炎症作用、ターンオーバー促進など、肌に多くの良い効果をもたらします。技術的な問題で現時点では化粧品成分としてはほぼ利用されていませんが、食事やサプリメント、あるいは日光浴(日光浴をすると体内でビタミンDが合成されます)によって摂取することができます。また、ビタミンK(フィロキノン、メナキノン)は血行を促進する効果があることが知られており、目の周りのクマを改善するためのアイクリームや、赤ら顔を改善するための化粧水などに利用されています。こちらも現時点ではあまりメジャーな成分ではありませんが、化粧品成分としてもっと利用するための研究が進められています。
このような「これからの成分」といった側面はビタミンDやビタミンKだけではなく、ビタミンAやビタミンBについても同様です。ビタミンA誘導体に関しては、レチノールの効果をなるべく損なわないようにしつつ、レチノイド反応などによる刺激を抑える研究が日々進められています。最近登場したレチノイン酸ヒドロキシピナコロンはレチノイド反応の原因となるレチノイン酸を経由せず、直接受容体に作用する低刺激な成分として注目されています。また、ビタミンB群についても、パンテノールの「エネルギーの代謝を高める」ことによる美白作用や葉酸の抗酸化作用など、様々な研究が進められています。
これらの基礎的な研究、製品への応用がより進められていけば、私達はビタミンからより様々な恩恵を受けることができるでしょう。ビタミンはありふれたようでいて、まだまだ大きな可能性を秘めた成分なのです。